

各国料理と音風景
エスニック料理が好きだ。 特にアジアには目がない。 それにしても東京はすごいところで、 なんでも食べることができる。 タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、インド、 ネパール、台湾、この辺りはポピュラーなので 当たり前のように見かける。...


増えつづける柱サイネージ
一般的にはデジタルサイネージといっている動く看板。 液晶やプラズマディスプレイが街のいたるところで見られるようになって久しい。 電機メーカーの生残り戦略もあって、すさまじい勢いで増え続けている。 見にくかった電光掲示板などが、カラフルで大きくなったのはいいことだと思う。...


消えゆく町の個性
好きな町のひとつに吉祥寺がある。 中央線文化と井の頭線文化が融合していて、 金持ちから貧乏学生まで 誰でも居場所を見つけられるところだ。 個人商店街が町の中心になっていて、 百貨店や大型商業施設は付録的な存在。 エネルギー感が町全体に漂う。...
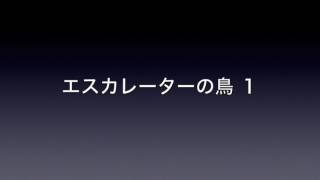
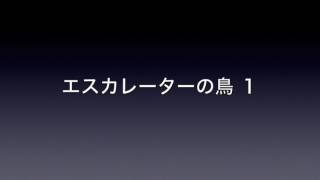
駅のバリアフリー音響
駅のホームで流れている鳥の鳴き声。 これ、気にしたことがあるだろうか。 10年ちょっと前から少しずつ増えてきて、今ではほとんどの駅で採用されている。 いろいろ聴いて回ったら、鉄道事業社によって鳴き声が違うことがわかった。 でも「鳥の鳴き声」っていうのは皆同じ。...


優先席を考える
電車やバスの優先席(プライオリティシート)はどれだけ役立っているのだろうか。 かつて横浜市営地下鉄は「全席優先席」だった。 当時、なるほどそういう考え方もあるよなあと思い、応援していた。 しかし2012年、全席優先席自体は残し「最優先席」を設けると発表した。...


鉄道高架化の弊害
昔は全ての電車(列車)が地上を走っていた。 田舎にいた子供の頃、線路土手に生えている土筆を取りにいき、 蒸気機関車が近づくとあわてて逃げたものだ。 トイレ付きの特急が通過するときは汚物に気をつけた。 昔は線路に垂れ流しだったのだ。...


おせっかいな店内放送(2)
店内放送、第2弾。 第1弾でも書いたように、開店や閉店のお知らせ以外にも、 「ランチタイムのお知らせ」「駐車場の案内」「ペット持ち込み禁止案内」 「禁煙案内」などなど、一日中定時放送は続く。 タイムスケジュールを見ると、だいたい10分に1回は何かが流れるようになっている。...








